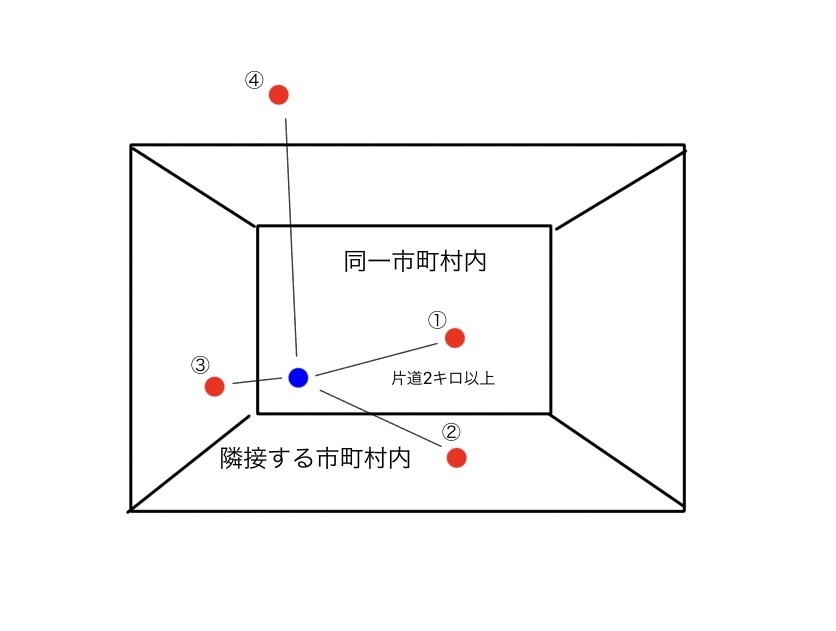労災保険の障害等級認定実務では、高次脳機能障害、脊髄損傷、非器質性精神障害の各障害については、主治医の先生に所定の様式を用いて意見を求めたうえで等級認定が行われています。
ここでは主治医意見書に関する認定基準の内容についてまとめています。
1.主治医等に対する意見書
主治医等に対して意見等を照会する場合の様式として、様式1・2・3があります。
(1)高次脳機能障害
診断書の傷病名の欄等に、頭部外傷または脳血管疾患等による高次脳機能障害が想定される障害が記載されている場合は、主治医の先生には様式1「脳損傷又はせき髄損傷による障害の状態に関する意見書」により、家族または家族に代わる介護者には様式2 「日常生活状況報告表」により、障害の状態についての意見を求めることが必要とされています。
様式1の裏面に記載されている「高次脳機能障害整理表」は、意思疎通能力、問題解決能力、持久力・持続力及び社会行動能力の喪失の程度別に後遺障害の例が示されており、主治医の先生がこれら4つの能力の障害に関する意見を記載するにあたって活用されるものです。
高次脳機能障害の状態について、家族または家族に代わる介護者と主治医の意見が著しく異なる場合には、再度必要な調査を行うことが求められています。
(2)身体性機能障害
診断書の傷病名の欄に、脳損傷または脊髄損傷が想定される傷病名が記載されているものについては、主治医の先生に対して様式1「脳損傷又はせき髄損傷による障害の状態に関する意見書」により障害の状態についての意見が求められます。
具体的には、麻痺の範囲等(運動障害の範囲・性状・起因部位、関節可動域制限の有無・可動域角度、筋力、感覚障害の範囲・性状)と麻痺の程度、介護の要否などについて意見が求められます。
麻痺の範囲と程度は、身体的所見及びMRI・CT等により裏付けられることが必要とされていますので、主治医意見書に記載されている麻痺の性状・関節可動域の制限等の結果と麻痺の範囲・程度との間に整合性があるか否か確認され、必要に応じて再度主治医等に調査を行ったうえで、障害認定が行われることとされています。
(3)非器質性精神障害
うつなどの非器質性精神障害については、主治医に対して様式3 「非器質性精神障害の後遺障害の状態に関する意見書」により障害の状態の詳細について意見が求められます。
具体的には、症状・治療の経過、精神症状の状態、能力低下の状態などについて意見が求められます。
2.留意点
労災保険の障害等級認定実務では、上記3つの後遺障害について、基本的には主治医意見書の回答内容に基づいて等級が認定されています。特に高次脳機能障害では、本人やご家族と主治医の先生の意見が大きく異なるおそれがあります。主治医の先生が本人の障害内容や程度を詳しく把握していないことがあり得るからです。
このため、できれば主治医の先生に後遺障害診断書を作成していただく段階で、詳しい障害内容や日常生活・お仕事でのお困り事をメモにしてお渡ししておかれますと、主治医の先生との見解の相違は少なくなると思います。
なお、労働基準監督署では、治療中の段階でも、主治医の先生に対して適宜文書で照会を行い、症状等の確認を行なっていますので、症状の一貫性なども審査の対象とされています。
以上
(令和7年5月21日作成)
【関連ページ】